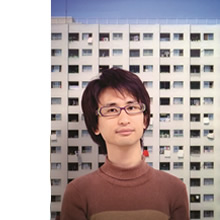2013年4月講座
「千葉の工場萌えと街づくり」
フォトグラファー・ライター
大山 顕 氏
今日は、大人の好奇心をくすぐる「ままならなさ」と「何となく」という2つキーワードを出して、今まで僕がやってきたことの紹介をさせていただきながら、それが一体どういう意味があるかということを考えてみたいと思います。
僕は団地マニアでして、学生時代に「団地ってすごくおもしろいな」と思ったのをきっかけに、全国の団地を見て写真を撮って回っています。SNS(ソーシャル・ネットワーキング・システム)もブログもなかった時代に、いわゆる個人サイトに団地の写真を撮って発表していたのですが、これがかなり評判になりました。現在は出版をしたり、イベントや写真展もやっております。
団地はみんな形が一緒だと思われているかもしれませんが、実は非常におもしろいのです。僕が「オデキ」と呼んでいる出っ張りがあったり、「タワー」と呼んでいるエレベーターがおさめられているところがあるのが特徴です。今どきのマンションは立面がきれいにデザインされていて、このような特徴はなくなってしまいましたが、エレベーターがそこにあるのだから出っ張ればいいじゃないかという団地の非常に実直なところにぐっときています。
上が王冠みたいになっている団地を「王様タイプ」と呼んでいます。東京メトロ東西線の西葛西駅を挟むように別の王冠が対峙しておりまして、団地マニアの間では「王家の谷」と呼んでいます。それから、東京・江戸川区の春江住宅は本体が小さ目なのにタワーが大きくて、僕は「春江たん」と呼んでいるのですが、身長が150センチなのにEカップのグラビアアイドルを彷彿とさせています。また、高島平にある団地は、エレベーターを降りると両側に扉があって、各戸にアプローチする形式になっています。あと、柱と梁が前面に出っ張ってベランダが奥まっている感じのものもあり、実は都営団地がみんなこの形で、ワッフルみたいなので「ワッフルタイプ」と呼んでいます。
ごつごつしていたり、大胆にV字型に折れ曲がっていたり、それでも奥にちゃんとオデキがあったりと形もいろいろですが、およそ21世紀の色彩感覚でないものを繰り出しているのが団地の非常におもしろいところです。タワーをそんなに塗らなくてもいいじゃないかと思うところもあって、この前見に行った王子の団地は、青いドットになっているところにピンクと黄色が付け加えられていて、恐るべきカラフルなものになっていました。
僕はこれまで形と色だけを見てきたのですが、軽薄であるとか、浅はかであるというようなことを言われて、批判を受けることもままあります。「団地って金持ちが住むところではないよね」というようにしか言われなくて、誰も形を見ていません。団地に限らず、およそ我々は都市というものを見ていないのです。「目にする」ことと「見る」ことは全く違います。写真を撮る人間は、おのずとそこら辺に意識的にならざるを得ないので、一度、街をちゃんと見たことによって、その先に何かあるんじゃないかと信じて今までやってきました。
僕は、団地のほかに「工場萌え」でもあります。船橋の準工業地域で育ったので、あの風景が懐かしくて当たり前だと思っていたのですけれども、大人になって、そうじゃないことに気づきました。それで、そんなのはおかしいと思って、千葉大の修士論文で工場を壊さずにコンバージョンして残したらいいではないかという提案をしました。工場というと世の中は公害の話にすぐ結びつけますが、僕らの生活を支えているのは工場だったりするわけで、普通にかっこいいと思ったので、2007年に工場の写真集を出しました。それまでアートの世界以外で工場の写真集というのはなかったのですが、出してみたら大当たりでした。
和歌山の精油所から川崎、鹿島、千葉という具合に、日本全国で工場の写真を撮って発表してきました。僕が工場を真剣に撮り始めたのは20年ぐらい前からで、当時は千葉大のそばに川崎製鉄さんがありました。高炉が4つも5つあってかなり大規模で、何てかっこいいんだろうと思って工場に目覚めたという思い出があります。ですから、第5高炉が解体されるときは、涙が出るほど悲しい思いをしました。
団地と工場以外にも、ジャンクションもかっこいいなと思っています。みんな高速道路だと思うだけで見るのをやめていますが、まじまじ見るとジャンクションの構造物はすごいことになっているのが写真を撮り始めてわかりました。本も出させていただきまして、ジャンクション好きの「ジャンキー」たちには結構人気があります。
僕以外にもジャンクション好きは昔からいましたが、みんな上から見るのが好きなんですね。航空写真とか地図を見て、ぐにゃぐにゃになって複雑に道路が入り組んでいるのを見てにやにやするのが趣味のようですけれども、僕は、ジャンクションは下から見るべきだと思っています。上からというのは日常の風景ではないので、それにはあまり興味がありません。それよりも、普段よく見ているのにスルーしているものを無理やり見せて、「僕らはすごいおもしろい街に住んでいる」と気づかせることができたら、僕の勝ちだというふうに思っています。
箱崎ジャンクションの隣に星付きのロイヤルパークホテルがありまして、上からの風景も一度は見ておこうと思って、ホテルに泊まって写真を撮ったこともあります。大都市に住んでいたら、日頃こういうものは目にしているはずなんですけれども、普段はあまりじっくり見たりすることはないと思います。既にいろいろなインフラが立て込んでいる大都市で何かをするとか、インフラをつけ加えるとか、新たなシステムをつくるとか、あるいはメンテのために補修をするということで、都市土木の難しさが端的に現れているのがジャンクションであり、よくも土地のないところにこういうものをつくったなとつくづく思います。それが時には非難の対象になりますが、東京を形づくっているわけですからこれは非常にダイナミックでおもしろいと思います。
ほかにも、ゴルフの練習場も不思議だなと思って、ずっと写真を撮っています。柱とネットだけの巨大な構造物が住宅の中に突如現れて、夜は照らされるわけですから、こんな奇妙なものはないのに、みんな「打ちっぱなしでしょ」とスルーしている。その視線のスルー具合も込みでおもしろいなと思います。あとは変電所のぐちゃぐちゃ具合とか、立体駐車場も、窓一つない背高のっぽの構造物が突如国道わきに現れて「P」と書いてあるのは、不思議だなと思って撮っています。
それから、アパートも、日本人ならみんな何となく同じイメージを持っているというのはおもしろいと思います。もはや新しくこういうアパートをつくったりはしないので、なくなる前にと思って撮っているのですが、全国に膨大な量があり最近はスローダウンしています。
あと、僕は「浮かれ電飾」と呼んでいるのですが、12月になると一般家庭がイルミネーションをつけるのが流行っているのも非常におもしろいなと思って、全国を回って撮っています。テクノロジーが人を助長させるというのはこういうことだなと思うのですが、ここ10年ぐらい見ていると、青色LEDができてから「浮かれ電飾」業界がすごいことになっています。アイリスオーヤマさんがSNSをつくっていて、「イルミネーター」と呼ぶらしいのですが、これをやるのが趣味の方々が自分の家のイルミネーション自慢をするコミュニティのサイトもあります。僕もこれを毎年見ているおかげで、流行があることがわかってきました。
郊外のホームセンターに行くと、11月頃から電飾コーナーが出来ていたりするのですが、5年ぐらい前は12月から始まっていたのに、今は早いところでは10月から始まっています。10月ぐらいからハロウィンを電飾で盛り上げて、11月に入ったら徐々にクリスマス気分になっていっていくのですね。商業施設の場合、ハロウィン、クリスマス、バレンタインが電飾の季節で、今のところはお正月が防波堤になっているので、「浮かれ電飾」はクリスマスで終わっています。でも、僕の予想では、今年とか来年あたりは「電飾門松」が出て来るんじゃないかと思っています。そうなると、2月のバレンタインに向けてそのまま行っちゃって、およそ半年間ずっと「浮かれ電飾」状態になってしまいますから、建売住宅では電飾を付けやすい仕様のサイリングとか外壁材になるのではないかなという気もしています。
あとは、改札口にある生け花も不思議です。誰が手入れをしているのか気になるところですけれども、今はだんだん形骸化しています。
ほかにも、僕は「高架下建築」と呼んでいますが、鉄道の高架下に住宅とか倉庫とか商店が入っているのもおもしろいと思って撮っています。兵庫の御影駅の高架下建築群とか、浅草橋、秋葉原、浅草とかは、非常にキュートだなと思って撮り続けています。大阪には相変わらず厳然としてあるのですが、東京にはどんどんなくなっています。京成線の下にもいっぱいあったのですけれども、耐震補強をしなきゃいけないということでなくなって、今は全部更地になっています。
皆さんに、工場がかっこいいとか、団地はおもしろいとか、これがキュートだということをお話しする機会をいただくようになってから、「何がおもしろいのか」とか、「共通して言えることは何なのか」ということを問われるようになったのですが、高架下建築を見たときに、ここに僕は惹かれているんだということがわかりました。
秋葉原の高架下建築にはおもしろいポイントがあって、高架の高さは一緒なのに、2階建て、2.5階建て、3階建てというようにいろいろなんです。僕はこれを見たときに、「そういうことか」と思いました。要するに、高架下というのは、そこで人が生活を営むためにあるのではないので、2階建てにするには高いけど3階建てにするにはちょっと低いみたいな中途半端な事態が起こるのです。およそ世の建築物で、人間が活動する都合に合わせて高さを決められない建築というのはないわけです。間口のほうはいい具合になっているのであまり不思議な感じはしませんが、高さは今述べたような中途半端なことが起こっているのです。2階建てにするのにはちょっと低いので、1階をすれすれのガレージにしていたりしています。
高架の場合は、いろいろな事情があって、デザインの論理ではなく鉄道側の論理が支配しているのがおもしろいと思います。退去してなくなったところに新しく入っているところは、プレハブみたいなものが中にすき間をあけて入っていたりするのですけれども、一昔前はみんなそういう状態でした。要するに、高さを意匠の論理で決められなくて、鉄道の論理が卓越しているので、それと折り合わなきゃいけないというままならなさが、僕がおもしろいと思っているものだと気づいたわけです。
これは、どこにどういう制約があるかを読んで、それを受けてどう折り合いをつけるかということだと思います。テクノロジーと工法が進化すると、マンションのように、ままならなさをテクノロジーが凌駕して無視できるようになったりすることがありますけれども、その制約をどう逆手にとるか、あるいはどう生かすか、どう折り合うかというところが見えなくなってしまうと、おもしろくないと思います。
後付けでかなり強引なんですけれども、団地がすっとんきょうな色だったり、ファサードがまともにデザインされてないのは、高度経済成長前夜からその後にかけて、とにかく都市部に大量に人口が増えて住宅がなかったからで、これは僕の定義ですが、マンションは商品で団地はインフラだと思っています。要するに、団地がつくられた当時は、限られた時間とコストの中で、とにかく住宅を供給しなければいけないという大量生産の論理が優先して、デザインは二の次だったのです。ところが今のマンションは、グレードにもよりますが、1階に大理石を張ったりしているところが団地とは違います。
パイプ床がぐねぐねになっている工場にも、全部に意味があるわけです。プラント設計の方から伺ったのですけれども、熱とか圧力とか振動からの安全性を考慮すると、ああいう形になるのだそうです。要するに、物理的にどうしようもないままならなさを相手に折り合った結果、ああなっているというのが、僕の目にはかっこいいと思って見えたのです。
ジャンクションも、交通工学の論理と、用地がないということに折り合った結果、4層にもなって複雑に立体交差することになったのだろうと思います。それで、僕はデザインを勉強したにもかかわらず、デザイナーが好き勝手できずにいろいろな制約のもとで四苦八苦やって、苦しい中で生まれてきた形がキュートだと思うようになったということがわかったのです。
僕は、工場の中でも、石油化学系の精油所よりもセメント工場と製鉄所がおもしろいと思っています。セメント工場には必ずパイプが、ぐねぐねと動物のような感じになっていて、これは何でなんだろうと思っていたのですが、石油化学系の精油所は、扱っているものがガスとか液体なので、圧力をかければ高いところに上っていくけれども、セメント工場が扱っているものは、石灰石とかの粉状のもので、重力とか摩擦の制約をすごく受けるため、パイプを水平にして渡すとパイプの中に粉がたまってしまうそうです。だから、たまっても中で落ちるように折り曲げているということを聞いて、なるほどと思いました。摩擦と流体力学的な論理がこの形を決めているというのは、おもしろいなと思います。要するに、セメント工場は重力の支配を受けるものを相手にしているので、見た目のままならなさがよく現れているのです。
最近、僕が非常におもしろいと思っているのが地形です。人間はお天道様にはかなわないというか、地形とか天候は相手に折り合わなきゃいけない一番の対象です。団地のレイアウトで言うと、ニュータウンは地形図と合わせて見るとおもしろくて、横浜の港北ニュータウンのレイアウトは、地形に合わせて四苦八苦していることがわかります。丘陵地のあたりは、造成された後がモザイク状になっています。
建築物の定義というのは法律で決められていて、天井があって他の境界と区切る壁と柱の構造を持っているのですけれども、僕が建築とは何かと聞かれたら、「床が水平であること」と答えます。建築物で一番重要なのは造成で、斜めの上に建築は建たないのです。一見、崖をまたいでいるところでも、もとの地形が人為的にモザイク状にどんどんなっていって、平らな部分が所有の区分であったりするわけで、1個1個見ると地形がなくなっているように見えるのですけれども、人間ができることはたかが知れているというか、対極的には地形は温存されていて、人間のいじらしさがかえっていとおしく思えます。ニュータウンはモザイクが大きいのですけれども、世田谷とか下町の崖っ縁のところは1軒1軒が小さいので、モザイクがもっと細かくなっています。
多摩ニュータウンはおもしろくて、頑張って造成したことがわかります。北側のへらで平らになでたみたいなところが多摩ニュータウンエリアで、南側のごつごつしたところに比べると、かなり頑張って真っ平らにしようとしているのですけれども、しきれないところが非常に印象的です。地形図を見ると、道路が谷筋を走っていて、ニュータウンの団地は全部尾根の上に立地しています。ですから別の街区に行こうとすると、必ず大通りをまたぐ陸橋みたいなもので横に移動することになっていて、地形との折り合いのつけ方が港北ニュータウンとは違います。
東京には団地が結構いっぱいあります。阿佐ヶ谷住宅もおもしろいです。そろそろ建て替えでなくなってしまうのですが、前川國男という有名な建築家が設計に携わった団地です。前川國男はコルビュジエの弟子と言われた人で、あまりにも神格化されているのですけれども、実はこれは何のことはなくて、善福寺川の蛇行に合わせた地形なだけなんです。要するに地形を読んだらああならざるを得なかったわけで、そのことのほうがキュートに思えます。
豊島五丁目団地は巨大団地で、北区の突端に境界が走っています。人工の荒川放水路ができた後も、昔の川の流れのまま境界をひきずっていて、川の氾濫に悩まされ続けてきたところなので、かなり盛られて水の対策をしていることがわかります。
隅田川の鐘淵も川の流れが蛇行しているのですが、ここに長さ1キロの白鬚団地があるのをご存じでしょうか。あそこら辺は超下町で、木造の古い住宅が密集しているので、地震が来たら火の海になることは昔からわかっているところです。消防車も入っていけないような細かい路地がいっぱいあって、どうにかしたかったようですけれども、地元の方は区画整理に反対を押し通しました。そこで、ここが火の海になったら、隅田川沿いの土手にある広域避難所に一旦逃げて、みんなが逃げたらファイヤーオールになるという団地をつくったのです。要するに、火を食い止める防火壁の役割を与えられているので、災害時にはシャッターが全部閉まるようになっています。いざというときにはベランダのシャッターが全部下りて、1枚の完全な壁になって火を食い止めるという恐るべき団地です。1970年ぐらいだったと思うのですが、当時、東京に7カ所ぐらいつくられる予定だったのが、直後に都知事が代わって方針が転換されたので、ここは幻の一品なんです。屋上には放水銃用の水がいつもためられていて、各所に放水銃がついていて消火活動まで行うという、ロボットのような団地です。
団地というのはなるべく南を向こうとするのですけれども、周りの敷地の向きとバランスが崩れているところもあります。典型的なのは埼玉の上野台団地で、団地は見事に南を向いているのですが、周りの敷地の向きと対照的になっています。ここは、昔の地図を見ると周りが全部田んぼなんです。そこに軍事工場ができて、戦後に団地として再開発されたのですけれども、日照の問題を考慮して敷地の向きに構わず全部南を向いていて、非常におもしろいです。周りの田んぼがぽつぽつと住宅化されていくと、その都度田んぼのグリッドに合わせて開発されていくので、団地が南を向いているのと極めて対照的な向きになっているわけです。田んぼというのは水を張って効率よく流さなければいけないのですが、昔の田んぼは、ポンプを使わずに重力に従って勾配をつけて平等に水を流していっているので、等高線を描くのです。田んぼはものすごく地形を読んでいて、お天道様相手と地形相手がせめぎ合った形になっています。
千葉大のそばに、甘太郎という体育会系が好むボリュームを売りにした定食屋があるのですが、僕は在学中から、ここの前だけ道が曲がっているのは何でだろうと思っていました。西千葉の駅前は比較的碁盤の目のようにきれいになっているのですけれども、ここだけ曲がっていてちょっと破綻しているのです。1970年の写真を見ても1961年の写真を見ても今と変わらないのですが、1947年の写真を見てその謎が解けました。総武線が開通したときに、周りの道が総武線に並行して走るようになって地形を読まなくなったのですけれども、甘太郎の前だけは、なぜかもとの地形に沿ったグリッドが残っていたのです。要するに、実はこっちがオリジナルで、周りが違っていたというわけです。
地形というのはおもしろいと思うのですが、僕が目下悩んでいるのは、大人の事情的ままならなさをどう考えたらいいかということです。一番のままならなさというか、制約というのは時間とコストで、こういう解決方法があったのかということでついた折り合いは、キュートだったりするのですけれども、地形とはちょっと違うのです。建築家の吉村靖孝さんが書いた『超合法建築図鑑』という本がすごくおもしろくて、ビルの形を建築基準法から読み解いているのですが、デザイナーがこうしたかったわけじゃなくて、法律が形になって現れているんだと思うと、これはキュートだなと思うのですけれども、そういうものをどこまでキュートだと思っていいんだろうかと悩んでいます。
団地にも同じようなのがあって、国立市谷保にある団地は、すき間を埋めるように建っていて、広い道があるけれども車が全然通らないのです。なぜかというと、南武線を高架にするかとかいろいろ計画がある都市計画で何十年も四苦八苦していて、今なお止まっているからなんです。道路を通すからという理由で敷地の形とか棟の向きが決められたのに、その道路がいまだに通っていないというのは、大人の事情です。
井の頭通り沿いは、すごい短冊状に細長く地割りがされているのですが、新田開発の後に各農家に平等に畑を与えようとしたときに、正方形に近づけると、そこにアクセスするために道路をいっぱい引かなきゃいけないけれども、細長くして間口を狭くすれば道路をそんなにつくらなくていいという論理でつくられているので、結果として短冊状になったそうです。これも大人の事情で、インフラをあんまりつくりたくないということから起きたことです。
中央線沿いはどんどん再開発が行われていって、新田開発のときに短冊地割りで所有した人が畑を売って宅地化している一方で、まだ畑で頑張っているという風景がいっぱいあります。
小平のあたりは、畑と宅地化されたところが入り乱れています。これは僕の勝手な予想ですけれども、相続した土地を切り売りしていった結果、多くは宅地開発されていったのですが、地面の代替わりを物語っているのではないかと思うのです。要するに、ここはかなり土地開発されていて2代ぐらい代わっているとか、ここはまだおじいちゃんが畑で頑張っているとか、ここは1代目が亡くなって、ここだけ売ったというようなことが現れているように思います。都市計画的には道路をもっと通したいんでしょうけれども、土地所有者全部と調整をつけないと道路を通せないわけですから、いつまでたっても渋滞しているんだろうなと思うと、この大人の事情のままならなさというか、所有というままならなさをキュートだと思っていいのかどうか悩みます。
そろそろまとめです。1つ目は、「ままならなさ」がデザインの論理を超えて、人がそれと折り合った結果を僕はキュートだと思っているので、それを見るとおもしろいし、実はそういうのをおもしろいと思っている人が結構いるんじゃないかという話をしました。
2つ目は、「何となく」を大事にという話をしました。工場好きなんてそんなにいないのではないかと思っていたのですが、結果的に『工場萌え』はすごくよく売れて、今はツアーもいっぱいあります。全国には、ああいうのが好きという人は結構いるのですが、同じ職場などで同好の志が生まれる確率はものすごく少ないので、私の趣味は変なんじゃないかなと思ってみんな黙っていたのです。ところが、ネットのおかげで自分だけじゃない、ひとりぼっちじゃないということがわかるようになって、カミングアウトしたのです。
僕は今、首都高さんとジャンクションツアーをやったり、商工会議所とか自治体の観光の担当の方と工場のツアーをやったり、クルージングの監修もさせていただいていますが、もともと10年ぐらい前からずっと個人的にツアーをやっていました。それはなぜかというと、僕は男だったので、周りに理解者がいなくても、一人で夜の工業地域を見に行って写真を撮ったりしていたのですけれども、女性が夜の工業地域とかジャンクションを一人で見に行くのは難しいことです。それでツアーを始めたのは、一緒に行ってくれる人が周りにいないというので悶々としていたことがわかったからなんです。そこで、「今週末、見にいくけど一緒に行く人はいますか」という乗りで始めたのが最初で、それが今みたいなクルーズに育っていって、熱心に参加してくれる女性がすごく多くなっています。
有明ジャンクション、川口ジャンクション、三郷ジャンクションという具合に見に行っていたのですけれども、それを聞きつけた首都高さんが「大橋ジャンクションをつくっているから、みんなで見に来る?」と言ってくれて、特別に見させてもらったりしました。あとは、首都高さんと一緒に船から首都高を見てみようというツアーもやりまして、みんな大喜びでした。
工場も、定期的にみんなで見に行っています。中には柵や緑地帯で見えないところもありますので、そういうところは2階建てバスを借りて見に行きました。バスは公道を走れるぎりぎりの高さなんですが、乗用車だと柵で見えないところが見えて、みんな夢中になっていました。今は僕がやってきたことが広く受け入れられているので、いい時代になったなとうれしく思っています。
「ドボ年会」といって、土木構造物を見る忘年会も3年ぐらい続けてやっています。東京の同じ趣味の人とも会いたいと大阪や北海道の人が言っているのを聞いて、年末ぐらいみんなで集まろうということで毎年募集しています。それがなぜか「ウォール・ストリート・ジャーナル」に載りまして、日本では今、こういうのが流行っているらしいという誤った情報が広まってしまったわけですが、マニアを相手にしていたら、こうはならなかったと思います。みんなが気軽に入れる入り口をつくるが僕のミッションだと思っていまして、「深いことは知らないけど何となく素敵」という人たちを相手にするように、いつも心がけています。
僕がウエブサイトを始めたのは、Face book もなければ、ブログもmixiもない時代でしたから、サイトを開設する人というのは、何か言いたいことがある人たちだけでした。今、コミュニケーションとかソーシャル・ネットワークとか言っていますけれども、僕は、ウエブの本質はまだパブリッシングだと思っています。ウエブに出会ったときは、出版社や新聞社の力もかりずにパブリッシングが自分一人でできる、何て夢のようなツールがあるのだろうと感動しました。いまだにその感動はありますけれども、そこでコミュニケーションをするのは間違いで、言いたいことがある人は、一方的にパブリッシングをすればいいと思っています。
マニアじゃない「何となく」という人たちは、コミュニケーションからは生まれなかったはずです。2009年に『ウェブはバカと暇人のもの』というニュースサイトの編集長の方が書いた本が話題になりましたが、ネット業界にずっと携わっていた彼は、ネットが嫌になってしまったのだと思います。他人をすぐ「死ね」とか罵倒しまくる人がいて気持ち悪いし、アイドルのたわいもないブログが絶賛されて、きゃあきゃあコメントで埋まるのも気持ち悪いことです。結局、ネットメディアで視聴率を稼ぐには、バカのためのコンテンツをどんどん載せるしかないというように言っています。でも、ネットというのは、ほんの少しのちょっと変わった趣味を持っている人たちにたどり着けばいいだけなので、視聴率を考えること自体が間違っていると思います。数が必要なビジネスを考えずにパブリッシングできる初めてのメディアなのに、今、ネットはどんどん誤った方向に行っていると思います。
Web2.0の時代にも、みんなでコンテンツをつくっていこうみたいなことが話題になりましたが、みんなでコンテンツなんかはつくれないというのが僕の意見です。僕は、一方的に「団地って素敵だよね」というパブリッシングをウエブでやったことによって、今こういうことになっていると思っているので、まだまだ第2、第3の「工場萌え」ブームみたいなものがいっぱいあるのではないかと思っています。
興味のレベルというのは、普通は関心があるかないかだけだと言われていますが、実はその間に膨大な「何となく」という領域があるのです。ところが、世の中で目立つのはマニアなので、「何となく」とは言いづらい。例えば鉄道ってちょっといいなと思ったとしても、鉄道マニアの世界はすごくなり過ぎていて、入っていけません。「何となく」が許されないことになっていると思うのです。僕は「何となく」という領域が実は一番広くて、そこには人がいっぱいいて、大人の好奇心というのはここにあると思っているので、ネット以前は見えなかったここを大事にしたいと思っています。
僕が一人でやれることには限界があるので、最近はどんどんほかの人をけしかけているのですが、そのときに、「好き」という言葉はすごく危険です。何かに情熱を傾けるからには、その人はこれが好きなんだなとみんな思うのですが、僕はそれは間違いだと思っています。人間が時間を使ったり情熱をかけるのは、別に好きなことでなくてもいいんです。人は、自分が理解できないものでマニアックに熱中している人に会ったときに、「好きなんですね」と言って終わりにすることが非常に多いと思います。だから、「好き」というのは思考停止ワードで、その人が好きなんだからしようがないというように、それ以上深堀りせずに済む言葉でもあります。
それの延長で、僕は「自分探し禁止」をテーマにした「うまくならない写真ワークショップ」を20回ぐらい続けてやっています。みんな写真は個人のパーソナリティーとか能力を表すもの、作品だと思っているけれども、僕はカメラでもっとおもしろいことができるのではないかと思っています。2時間歩いて自分の好きではないものを撮ってもらって、最後に発表してもらうということをやっているのですが、最初はみんな半信半疑で撮り始めます。
ところが、しつこく撮っているうちに、好きではなかったはずなのに「撮るものがいっぱいあって、うれしい」とか、「おもしろいのがありました」とか言い出すんです。そして最後の発表では、「これはかわいい」とか、「こういう特徴がある」というように、どんどんしゃべり出します。自分の個性が表れている作品じゃなくて、人のせいにできるとなった途端、生き生きし始めるということがよくあるのです。要するに、僕らは何かに熱中すると、その対象物のことがよくわかるようになると思っていますが、実は逆で、のめり込めばのめり込むほどわからなくなることのほうが多いのです。
僕は、カメラというのは、都市にはおもしろいものがいくらでもあるということに気づくための道具であって、作品づくりのための道具ではないと思っています。ところが、みんな作品をつくりたいと思っているので、自分探しをして追い詰められてしまうのです。そうさせないための仕組みとして、「好きじゃないものを撮る」という追い詰めることをやっています。表現におけるオリジナリティーとか自己責任というのは、やめたほうがいいと思うのですけれども、やめるのはものすごく大変なので、抜け出すということをさせているわけです。
僕が好きなスーザン・ソンタグの言葉に、「自分自身について、あるいは自分が欲すること、必要とすること、失望していることについて考えるのはなるべくしないこと。自分については全く、または少なくとも持てる時間の半分は考えないこと」というのがあります。僕らは、ほっとくと自分のことをずっと考えています。「工場萌え」がブームになったのは、時には人のせいにして到達できることもあるからだと思います。自分のことばかり考えるのをやめたときに、こういうことを楽しんでもいいんだという、何かおもしろい発見があるのではないでしょうか。その先にはビジネスの種があるのではないかなと思っています。
時間も来ましたので、ここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。(拍手)
(了)