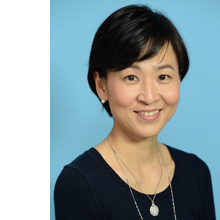2014年6月講座
「科学ニュースの裏側」
毎日新聞デジタル報道センター編集委員
元村 有希子 氏
私が新聞記者になったのは理科が苦手だったからです。高校を卒業するまで理系コースにいたんですが、成績がよくなくて文系に転じたという過去がありましたので、科学とは関係ない仕事をするつもりでいました。ところが、2001年に科学環境部に配属になって実際に取材を始めてみると、教科書を通して学んだ理科とは全く別物の、とてもおもしろい世界だということに気づきました。それからは楽しくて13年間も取材をすることになりました。
科学ニュースは、テレビ、新聞、インターネットなどで読まれています。私の13年間の経験の中で、新聞に載せて反響が大きい、あるいは大きな扱いになることが多いニュースの1つは、自分たちの生活に「歓迎しない何か」をもたらすような記事です。原発事故とか大地震、津波、温暖化、環境問題などです。そして、それとは反対のめでたいニュースとしてはノーベル賞があります。
日本人で最初にノーベル賞を受賞したのは湯川秀樹さんで、1949年のことでした。湯川さんは物理学者でした。それ以来、平和賞、文学賞も含めて19人の日本人がノーベル賞に輝いています。国別ランキングでは世界で8番目になります。1番はアメリカで、多分300人近くいますが、これは実は英語を使えるか使えないかというのがとても大きくて、日本語で生きている私たちは発信力がどうしても弱くて、とりわけ文学賞とか平和賞というのは、なかなか取りづらいと思います。
ロビー活動も大切です。ノーベル賞は公平に選ばれているというイメージがあるかもしれません。実際に公平なところもありますが、選考委員会がその年のテーマを決めるときに、ロビー活動の成果が出ます。日本はストックホルムに特にコネがあるわけでもないので、まだまだもらえる「のびしろ」があると思います。自然科学3賞の受賞者は16人。医学生理学賞が2人しかいないので、相対的に物理、化学が強いといえます。
2002年に小柴昌俊さんと田中耕一さんが物理学賞と化学賞を取ったときに、私も取材で行ってきました。晩餐会と授賞式では、報道陣もドレスコードを守ることになっています。女性は民族衣装、あるいは裾の長いドレスと決まっているので、出張経費としては認められませんでしたが、6~7万円のドレスを買っていきました。2012年に山中伸弥さんが医学生理学賞を取ったときに、担当だった女性記者にそのドレスを貸してあげました。結局、授賞式、晩餐会とも抽選に漏れて、ストックホルムまで行ったのに中に入ることはできませんでした。
もともとセレモニーには1,300人しか入れません。そのうち各賞の受賞者の身内の人たちが30人ずつぐらい入るので200~300人、あとは各国の大使とか招待客が入ると、マスコミの枠は20人ぐらい。だから、チケットをゲットするのは運と実力の賜物なんです。スウェーデンのノーベル財団は、日本メディアからはまず共同通信とNHKと、あともう1社という感じで選びます。その「あと1社」に入るのが結構大変です。
注目していただきたいのは、自然科学3賞の16人中11人が2000年以降の受賞です。2001年に科学環境部に来てから私は10人のノーベル賞受賞に立ち会っています。「科学技術基本計画」という、科学技術における憲法みたいなものがあるんですが、そこにはかつて「ノーベル賞に代表される国際的科学賞の受賞者を欧州主要国並みに排出すること。50年間でノーベル賞受賞者は30人程度」と書かれていました。数値目標を掲げて、取れそうな研究に研究費を付けるとか、ストックホルムに常駐の事務所を置いてロビー活動をさせるとか、ノーベル賞の選考委員を別の口実で日本に招いて最先端研究を見せるとか、そういう取り組みが実ったという人もいます。一方で、「50年間に30人も受賞するわけがない」と言っている人もいます。
ノーベル賞というのは、業績を上げてから受賞までの「待ち時間」が長いんです。山中さんは異例に短くて、2006年のiPS細胞作製の発表から6年しか待ちませんでしたが、あとは大体15年から50年──50年というのは南部陽一郎さんですね。ですから、ノーベル賞をもらうためには、優秀な研究者であるということに加えて、長生きが不可欠です。ノーベル賞は生きている人にしかあげないという決まりがあって、少なくとも選んだ時点では生きていないといけないんです。
もう1つ知っておきたいことは、2000年ごろから、国が研究費をたくさん投じるようになった効果で受賞者が増えたのではないということです。業績を上げた年はずいぶん前ですから、辻褄が合わない。つまり、彼らが業績を上げたのは、伸び伸びと研究をできていた時代であるというところがポイントです。最近は研究に余裕がなくなってきて、上から成果を出せと急かされるので、息の長い研究とか、びっくりするような研究成果を生み出せなくなっているという指摘もあります。
英国のピーター・ヒッグス氏も50年待ちました。1964年、物理学の理論を共著論文で提唱して、「ヒッグス粒子」と呼ばれる質量の源の素粒子を予言したんですが、ようやく理論が実証され、2013年に物理学賞を取りました。素粒子の話というのはとても難しいので記事にするのはすごく大変なんです。
さて、ノーベル賞は、発表当日まで誰がもらうのかわかりません。日本時間の午後6時半~7時ぐらいに発表され、そこから「用意ドン!」なんです。朝刊を印刷し始めるまでの3時間ぐらいで、分かりやすい記事を書かないといけませんから、緊張を伴う作業です。そこで記者はヤマを張って、「自分が選考委員だったら今年はこんなテーマでこの人を選ぶ」と大まじめに予想します。例えば理論提唱や発明から○周年とかいう節目がないか。過去20年ぐらいの受賞テーマを並べると、法則性が見えてきます。ある年が実験の成果だったら、翌年は理論に贈るとか、対象も素粒子の次は宇宙、宇宙の次は物質など、ある程度の繰り返しがあるんです。山中さんのときは「いつ来てもいいように」と準備していたので、それほど慌てませんでした。2010年に鈴木章さん、根岸英一さんが化学賞を分け合うことも当たりました。これは4、5年に一度の頻度で有機化学分野が受賞するということと、有機化学が強いのは日本だということからヤマを張り、いろいろ情報収集して予測を立てました。
慌てないための工夫として、ある程度の候補者リストを作って保管しています。毎日新聞の場合、自然科学3賞でノーベル賞級の研究者をリストアップしておき、事あるごとに取材に行って、怪しまれながらも子どものころの写真をお借りしたりして、その方がいつ選ばれてもきちんとした紙面ができるように準備をしています。
そうした準備ができなかったのが、田中耕一さんでした。発表された瞬間、田中さんのことを知っている科学記者は恐らく日本に一人もいなかったと思います。島津製作所の技術者で、博士号も持っていませんし、完全にノーマークでした。とりあえず島津製作所に電話をしました。広報課長さんが出たので「田中耕一さんという御社のエンジニアの人がノーベル賞に選ばれているんです」と言うと、相手は絶句して、背後で広報課の電話がいっせいに鳴り始めました。その頃、当の田中さんは実験をしていて、電話が鳴ったので出たら、「我々はあなたにノーベル賞を差し上げたいから10分後に発表する」と英語で言われたそうです。「今のは何だろう、なんかノーベルとか言っていたぞ」と部屋をうろうろしていたら、ほどなくして社長室に連れていかれて、そこから大変な日々が始まった、とご本人からお聞きしました。
こんな風に、ご本人もびっくりするぐらいノーベル賞は秘密主義なので、私たちが知るわけがない。そんな中で、発表されてから15分ぐらいで号外を刷り始めないといけませんから、この緊張たるや大変なもので、ヤマが外れたら徒労感があるし、知らない人だったらアドレナリンがすごい勢いで出て、全員で記事をつくるんです。
科学記者にとってノーベル賞というのは年に1回、瞬発力や取材力を試されるいい機会であり、いい刺激になっています。普段の取材の蓄積が生きるという意味でも、とてもいいトレーニングの場です。例年、10月上旬の月・火・水曜日に発表されます。私にとってはドキドキしなくて済む初めての年なので、楽しみで仕方がありません。
トピックとしては、今年こそ村上春樹さんが文学賞に選ばれるかどうか、そして個人的には日本国憲法9条に平和賞を、という推薦活動が国内で盛り上がっていて、実現したらおもしろいと思っています。
さて、日本で科学技術というと、欧米から輸入した西洋的な科学技術のことを言います。明治維新後、最初は教えてくれる外国人ごと雇い入れたんです。その1つが世界文化遺産に登録された富岡製糸場でした。戦争の時代になると、「科学技術は戦争に使える」という発想で、別の使われ方をします。戦後は「科学戦に負けた」という反省に基づいて、科学技術あるいは科学教育を強化しました。実際に高度経済成長でそれが実現したかに見えましたが、1960年代後半~1970年代に公害が明らかになって、「科学技術は夢ばかりを与えてくれるものではない」と気づき始め、科学技術と日本人の付き合い方が少し変化したと言われています。
私は1960年代生まれですが、子どものころに電気冷蔵庫やカラーテレビが家に来た経験をしているので、科学技術は便利で暮らしを豊かにしてくれるものという気持ちを持って育ちました。でも新聞記者になってから、阪神・淡路大震災やオウム真理教の地下鉄サリン事件がありました。オウム事件では、サリンをつくった人や、ばらまいた人の中に理工系の学生やお医者さんもいました。科学を悪く使えば幾らでも悪いことができる。良いほうに使わなければいけないのに何が欠けているのか、という不信が多くの人の間に広がったと言われています。
私にとって一番鮮烈だった科学事件は、東日本大震災と原発事故でした。3月11日当日は、津波と大地震に振り回され、12日以降は原発が大変なことになりました。1面トップの記事は連日、原発だらけになります。地震と津波で2万人近い方が死亡・行方不明になったというのに、原発のニュースに押しやられて腹立たしい思いがしました。
科学記者の取材分野は、原発はもちろん地震予知に関する研究ですが、地震予知には失敗、原発の安全神話も破綻しました。科学記者としてうそつきの片棒を担いだような無力感を感じました。日本政府は、「地震は予知できる」という前提で巨額のお金を地震予知研究に投じてきましたが、予測していた規模がマグニチュード8.0ぐらいだった。全ての人がそれを前提に防潮堤をつくっていました。ですが、実際に起きたのはマグニチュード9.0。マグニチュードが1違うと、地震の規模は33倍違います。
私たちは、原発の点検ミスやトラブル隠しが発覚するたびに、「こんなことで原子力の安全が守られるのか」という批判記事をたくさん書いてきましたが、ここまで大変な事態が起きるとは、正直想像していませんでした。特に批判を浴びたのは、「マスコミは東京電力と政府の大本営発表をうのみにしている」と言われたことです。ただ、官邸ですら東京電力のデータ頼みという状況で、しかも、東京電力が計算を間違えたり、故障に気がつかないといったデータ不備もあって、結果として間違った情報が流れたこともありました。
文部科学省科学技術政策研究所の調査では、「科学者の話は信頼できると思いますか」という問いに対して「信頼できる」と答えた人の割合が、震災前には84.5%いたのに、震災直後は40.6%にまで下がったというデータがあります。例えば「直ちに影響はない」という言い方をされると、「長期的には影響があるのかな」と不安になりますよね。これはその時点で「影響はまったくない」と言い切るだけの科学的根拠を誰も持っていなかったからです。科学者というのは、本当に裏付けられたことしか断言しません。だから、判断を仰がれるとあいまいな物言いをしてしまい、答えを待っている側にとっては納得できないものだったと思います。
ここに科学と社会のギャップがあります。私たちは、わからないことが起きた場合に専門家に意見を求めます。そして、無意識のうちに「安全だ」とか「心配無用」という言葉を待っています。もちろん「子どもは外で遊ばせちゃいけない」とか、「福島の野菜は全部食べるな」と言い切る研究者もおられましたが、最も求められたのは市民の不安に寄り添いながら、「わかっていること」「わかっていないこと」をちゃんと区分けした上で、アドバイスできる専門家でした。
専門家に取材して記事を書く私たちも悩みました。例えばホウレンソウから微量のセシウムが検出されたという時に、「この程度なら食べて大丈夫。食べないことによる栄養不足のほうが心配」という研究者がいる一方で、「被ばくは少ないに越したことはない、食べない方がいい」という研究者もいる。私たちは双方のコメントを載せるしかありませんでした。
このように、白黒はっきりつかないことに対して、科学というのは万能ではありません。科学は良くも悪くも社会全体を大きく変える、そんな時代になっています。「トランス・サイエンス」という考え方があるのですが、科学の成果が思わぬ副作用を生み出した場合、その責任は研究者だけでなく、社会全体で負うべきだ、というものです。原発で言えば、原子核が2つに分裂する核分裂を見つけた科学者を「あなたが核分裂反応を見つけなければ、原発もなかったし事故も起きなかったのに」と責めるようなもので、あまり現実的ではない。つまり、原子力の恩恵を享受してきた私たち自身が、原子力の厄災についても解決しなければいけないということなんです。その時に、科学だけでなく政治、公共政策、哲学といったさまざまな専門家が協力しあうべきだ、と40年も前に提唱されながら、日本の現状はできていない。
私の個人的な考えですが、科学者は、自分の好奇心を追いかけるだけでなく、発明を社会が受け入れた結果、歓迎しないことが起きるかもしれない、そのときにどうするかも考えないといけないと思います。生殖補助医療は、もともとは家畜の繁殖のために編み出された技術ですが、人工授精とか顕微授精を人間に使ったら便利だと思う人が現れて、多くの夫婦が恩恵を受けました。しかし、これが進みすぎて、夫婦じゃないカップルが子どもをもうけるとか、他人のおなかを借りて子どもを作るといった事態が起きたら、私たちは「これはダメです」とは言えないわけです。
ロボットについても、安倍政権は成長戦略で研究を推進する方針ですが、例えばロボットに子守をさせるとか、介護施設で職員の代わりにロボットを入れるとなると、「職をロボットに奪われる」「ロボットに介護されてまで長生きしたくない」という意見も出てくるでしょう。こういったトランス・サイエンス的課題が増えてきている世の中にあって、解決に動ける人を育てることが、これから重要になると思います。
次に、科学ジャーリズムについてお話しします。毎日新聞社に「科学部」ができたのは1957年12月です。スプートニク・ショックの後です。この年は研究用原子炉で初の臨界を達成したり、前年には科学技術庁が発足したりといろんな科学の出来事がありました。でも、その源流は1954年の第五福竜丸事件だと思います。
この事件は、太平洋ビキニ環礁で米国の水爆実験に巻き込まれ、死の灰を浴びて23人が被爆したというものです。各新聞社に科学部がない時代で、船が戻ってきた焼津の記者たちは大変な思いをしたようです。
私が第五福竜丸事件を科学ジャーナリズムの「原点」と考える理由は、この時に初めて原子力を理解する記者の必要性が高まったと思うからです。また、第五福竜丸の無線長だった久保山愛吉さんは「原水爆の被害者は私を最後にしてほしい」と言い残して亡くなったと伝えられていますが、これをきっかけに日本で原水禁運動が始まります。ヒロシマ・ナガサキではなくて、敗戦の9年後に始まったのです。
第五福竜丸はいま、東京の夢の島に展示されています。舟がここに捨てられていたことに疑問を感じた人々が市民運動によって保存につなげたということも含めて、科学の事件がジャーナリズムの文脈で扱われた出来事でした。新聞社は政治や経済、外交ニュースで新聞作りを始め、戦後は科学の知識を必要とするニュースが登場し、そこから科学との付き合い方を問い直すようなジャーナリズムが生まれた。
第五福竜丸が焼津に帰ってくる直前の毎日新聞に、「原子力が未来を変える」的な明るいトーンの記事が載っていました。原子力エンジンを搭載した汽車は超特急として使える、といった記事でした。科学の成果を無批判に受け入れていた新聞社が、科学を懐疑的に見つめ、ジャーナリズムの視点で記事にする。そのきっかけが第五福竜丸事件でした。
科学ジャーナリズムはようやく還暦を迎えたところです。人間も還暦を迎えれば成熟を求められます。科学環境部も、私が2001年に来た時には12人だったのが、21人まで増えました。さらに、いろいろな出来事に科学技術の知識が必要とされる場面が増えて、今では社内におけるシンクタンク的な役割も担っています。
成熟した科学ジャーナリズムの汚点の1つになるかもしれないのがSTAP細胞をめぐる捏造事件です。
私たちがこのニュースをキャッチしたのは今年1月下旬でした。こういうニュースが出るのは、論文が発表されるタイミングなんです。この時は1月28日に理化学研究所の記者会見があって、30日の朝刊に載せましたので、「知っているけど秘密」という時間が丸一日ありました。というのも、科学のニュースは複雑で難しいので、1日以上前に記者会見を開いてもらい、その代わり正しく報道します、という紳士協定みたいなものを研究者とマスコミの間で結ぶことがあります。今回はそれを踏襲しました。
結論から言うと、論文に間違いがあったということで、一報は誤報になりましたが、誤報とわかればそれをきちんと訂正する必要があります。ということで、「間違いだった」という記事も一面のトップニュースになりました。
実は、こういった研究不正は結構あるんです。例えば、10年前にソウル大学の教授が「ヒトクローンES細胞をつくった」と有名雑誌に論文を載せたんですが、それがウソだったということがありました。日本でも、2012年に東邦大学の元准教授が論文を大量に捏造していたことが分かりました。手術麻酔で使う薬の投与量と、麻酔が冷めた時に副作用として出る頭痛との関係を臨床試験で明らかにした論文でしたが、全く実験をやらずに180本以上も捏造していました。あとは、去年から毎日新聞がスクープして追及している降圧剤バルサルタンの臨床試験をめぐる不正があります。これは不正にかかわった研究者が逮捕されているので、今後どうなるかが注目されています。これ以外にも、私たちは年に何回かは情報提供を受けて研究不正疑惑を取材しています。
STAP不正を私なりに総括しますと、これは科学が宿命的に持っている「不確かさ」というものを露呈した1つのケースです。というのも、雑誌に論文が載る時点では、中身はまだ仮説なのです。つまり、ある研究者が自分の成果を論文にまとめて一流雑誌に載せて、発表と同時に世界の研究者の目に触れる。世界の研究者たちが追試をやって、「私もできた」「僕もできた」という検証が続いて初めて知の財産、あるいは公の発見として認められる。ですから、もしも捏造論文を書いても、載ってしまえばこっちのもの。ただ、載せた後に捏造がばれると困るから、みんなしないわけです。
報道も、世界中の人が追試して「間違いない」と太鼓判を押すまで待てばいいんですが、それだと「早く伝える」というジャーナリズムの原則に反してしまいます。その代わり、記事では「理化学研究所のチームが○○を見つけたと発表した」というふうに書いて、「○○が見つかった」とは書きません。言いわけのように聞こえますが、仮説が今後、本物の発見になっていってほしいという気持ちを持って書いています。
また、今回は捏造や意図的な不正によって論文が撤回されましたが、悪意のない勘違いによって撤回する例もたくさんあります。
こうして検証された結果、生き残った研究というのは、そこから大きな発見が生まれたり、応用されてノーベル賞を取ったりして公の財産になっていきます。さきほど「ノーベル賞をもらうまでには時間がかかる」と言いましたが、これはノーベル委員会の1つの作戦でもあります。慌てて授与して、それがウソや捏造だったら困るので、慎重に構えています。
STAP不正は、「査読」という審査を経ても事実とは限らない、ということを示しました。そして、現象そのものよりも、生み出した人に注目が集まってしまって、「どこが不正なのか」という論争をよそに「小保方さんに罪はない、許してやりなさい」といった意見が出て来て、場外乱闘のほうが注目を浴びたところもありました。それから、論文をネットで検証してウソや不正を見つけるという流れ、社会的査読とでもいう動きが強まっていて、それが機能したケースでもあります。
いずれにしても今回の騒動の背景は複雑です。科学報道に携わる者にとっては素敵な女性がノーベル賞級の発見をしたというニュースはなるべく大きな記事にしたいと、懐疑的な視点が欠けていた。理化学研究所も、成果はPRになるし、特定国立研究開発法人に昇格すれば多額の研究費がもらえるということでちょっとオーバーになった。さらに「ネイチャー」という雑誌も、厳正な審査をやっているとはいえ、広告と購読収入で成り立っている商業誌ですから、この成果を独占掲載することで注目を浴びて読者を増やそうという思惑があった。それらが一致した中で起きたのではないかと思います。
そもそも科学ニュースの対象は、科学的な手続きを踏んだ研究成果であることが最低条件です。健康食品などはそれを踏襲していないものが多いので、私たちが記事にすることはほとんどありません。学会で発表するだけではなく、論文にして雑誌に載るまで待つこともやっています。軽々しく記事にして失敗した例が結構あるのです。また、同じ分野の専門家に必ず取材して、内容を評価してもらい、それを踏まえて記事にします。STAP論文は全て「文句なし」のケースでした。
科学記者としては、関係者の処分の行方を見きわめることがこれからの取材になります。小保方さんが解雇されるかどうかだけでなく、彼女を盛り立てた他の研究者たちがどんな処分を受けるか。それから、彼女がいた研究所は第三者機関が解体を勧告しましたが、ここは日本の生命科学研究のトップランナーで、優秀な研究者が集まっている組織なので、どうなるのかについても関心があります。
同時に、STAP現象というのは、もしも本当にあったらとてもおもしろい生命現象だと私は思います。生きた細胞をオレンジュースぐらいの酸性液に30分浸すと出来る万能細胞。おとぎ話みたいなこの仮説が本当なのかどうか、検証に値するとは思いますが、お金も時間もかかりますし、その作業に従事する研究者がどれだけいるか疑問です。「もし他の誰かがSTAP細胞を見つけたら、小保方さんは最初の提案者とみなされるのか」と聞かれますが、彼女は論文を撤回しており、彼女が研究の世界で再び脚光を浴びることはちょっと難しいと思います。
教訓として、こういう不正が起きないために学術界がどう変わらなければいけないか。最近は研究にも「3年以内に成果を出せ」とか「5年以内にネイチャーに載せろ」とか「特許を取れ」とか、企業のような目標が課せられて、古きよき時代の研究スタイルが、残念なことにほとんどなくなっています。もちろん、研究費の多くは税金で賄われているので、「社会のために研究をしている、成果は社会に役立てる」という感覚を研究者に持ってもらうことは必要なのですが、それが行き過ぎると、成果が出ないので写真を切り張りする、というようなことが起きる。あるいは部下に圧力をかけ、部下が捏造をしてしまう。
特に、博士号を持っている若い人たちの3割以上は、3~5年契約の非正規雇用ですから、成果を急ぎがちです。そういう環境こそ何とかしないと、第2、第3の小保方さんが出てくるのではないか。ここは科学をウォッチする記者として一番心配なところで、日本の科学の健やかな発展を阻害する話になりかねないと思っています。
時間になりましたので、ここでお話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。(拍手)